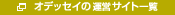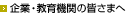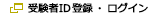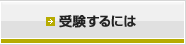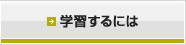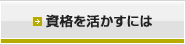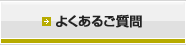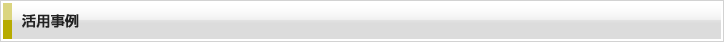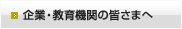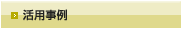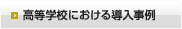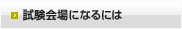同校情報科主任の原田貴裕さんにお話をうかがいました。
どのようなきっかけでIC3を導入されたのですか?
私が、IC3の存在を知ったのは、2005年のことです。『合格情報処理』という情報処理技術者試験などの受験対策誌を読んでいたときに、たまたまIC3の紹介記事を見つけました。
その記事により、コンピュータそのものの基礎知識、ネットワークの基礎知識、アプリケーションソフトの操作という3つの分野に関して、必要なスキルを個別に評価できるIC3のことを知り、とても興味を持ちました。
また、それまで本校の学生が受験していた検定試験の一部が2005年度を最後に廃止されることになり、学生に受けさせる検定試験の内容を一から見直すことになったため、2006年度からIC3を正課の授業に採用することになりました。
数多くある資格のなかでIC3を選ばれた理由は?
最近の学生は、中学校や高校の授業や家庭などでコンピュータに触れる機会が増えているため、WordやExcelなどのアプリケーションソフトの操作には長けています。が、その一方で、“コンピュータの基本”についてはきちんと理解していないケースが多いようです。
しかし、昨今の企業では、ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェア全般の知識を持つ人材が必要とされていますから、アプリケーションソフトが使えるだけでは、ビジネス界で役立つ人材にはなり得ません。私がIC3の導入を勧めたのは、この3科目の学習を通じて、コンピュータ全般の知識をまんべんなく身につけることができる、うってつけのツールだと思ったからなのです。
さらにIC3は、『初級システムアドミニストレータ』のような上級資格の取得に向けた、基礎的な知識やスキルを養うためにも非常に役立つと思います。
“短期集中型”の授業スタイルを採用しているとのことですが。
1年後に受験する資格の勉強を今から行っても効率が悪く、効果的ではありません。長い期間をかけて少しずつ学習していくよりも、むしろ短期間のうちに集中的に勉強したほうが効果的だと考えました。
IC3は、試験日を学校や学生の都合で自由に設定できますから、ほかの検定の試験時期なども考慮しながら、最適なタイミングでの受験日を設定しています。
この、短期集中型の授業スタイルが功を奏したこともあり、2006年6月に2年生が「コンピューティング ファンダメンタルズ」を受験した際には、約6割が見事合格しています。さらに、同年7月に「キー アプリケーションズ」を受験した1年生に至っては、ほぼすべての学生が合格を果たしました。
学生たちにIC3の取得を通じて、望むことは何ですか?
私は、IC3の資格取得は単なる通過点に過ぎないと考えています。何のために資格を取得するかと言えば、社会で必要とされる人材になるためです。IC3は国際資格ですから、努力して取得した結果が学生の自信につながることには間違いありません。
しかし、エキスパートとして活躍するためには、さらに“上”を目指す必要があり、そのためにも、まずは基本的なところを押さえておくことが重要になります。
そうした点からも、本校の学生たちには、付加価値の高い人材になるためのステップとして、IC3を存分に活用してほしいと願っています。
※掲載内容は2006年8月取材時のものです。