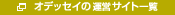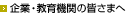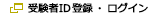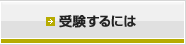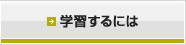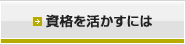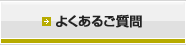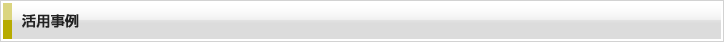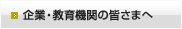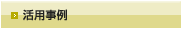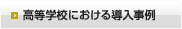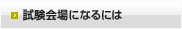京都光華女子大学人間関係学部メディア情報専攻では、2004年度からIC3の内容に完全対応した科目を取り入れています。
IC3の導入を推進した同学部の阿部一晴さんにお話をうかがいました。
阿部さんがIC3に着目した理由を教えていただけますか。
情報化社会である現在、パソコンなど情報機器の使用法や活用法といった、いわゆる「情報リテラシー」はすべての学生に求められています。けれども実際の学習範囲やレベルに統一的な基準を設けることは難しく、通常は「多少使える」とか「あまり使えない」というあいまいな区別しかできません。この点にはどこの大学でも苦慮していると思いますが、特に私たちのような情報メディアを研究・教育の対象とする大学においては、その前提として情報機器に関する基礎知識が必須のため、最適な基準を探していたんです。
情報リテラシーを見るための試験としては、すでに別の大学などでも採用されているものがありましたが、実際に就職後の現場などで求められるスキルをバランス良く盛り込んだ試験は、私が見る限りIC3だけでした。
IC3はコンピュータそのものの知識、ネットワークの知識、アプリケーション操作の3つの範囲について、必要なスキルを個別に評価することができます。
情報リテラシーのスキル・知識の客観的な到達評価基準として、世界的に実績のある点にも注目しました。本学への導入を提唱した2003年時点では、日本でスタートしたばかりだったIC3の認知度は低かったのですが、IC3と一蓮托生の思いで、正式カリキュラムへの導入を決意した次第です。
具体的にはどのようなカリキュラムを採用していますか。
2004年に人間関係学部人間情報専攻(現在は「メディア情報専攻」に改称)1年生向けに開講された半年の2科目、「コンピュータ基礎」(前期)と「ネットワーク基礎」(後期)において、IC3の「コンピューティング ファンダメンタルズ」と「リビングオンライン」の全範囲を網羅するカリキュラムを採用しました。この2科目に加えて、一般教養系の実習科目に通年の「情報処理」が用意されており、前期のWord、後期のExcelの実習を通じてIC3の「キー アプリケーションズ」の出題範囲をカバーできるようになっています。
つまり、上記3科目を受講することでIC3の2005スタンダードに対応した範囲すべての受験対策が完了する、という仕組みです。各科目は選択科目として他の専攻生にも開放されており、「コンピュータ基礎」について2004年は60名弱、2005年は約70名が受講しました。
IC3対応のカリキュラムを導入して、学生さんの反応はいかがですか。
受講した学生からは「学習内容が標準化されているので、勉強しやすい」「合格に向けて目標設定がしっかりできる」など、ポジティブな意見が多く聞かれました。
資格試験というのは、合否よりもそこに向けて学習する姿勢こそ大切。IC3の取得もコンピュータについて学ぶきっかけを得るという、学習過程に本当の意味があると思っています。
その意味では学生が自発的に学習に取り組めて卒業後にもすぐに役立つ、IC3対応のカリキュラムを本格導入したことは、成功だったと考えています。
※掲載内容は2005年7月取材時のものです。